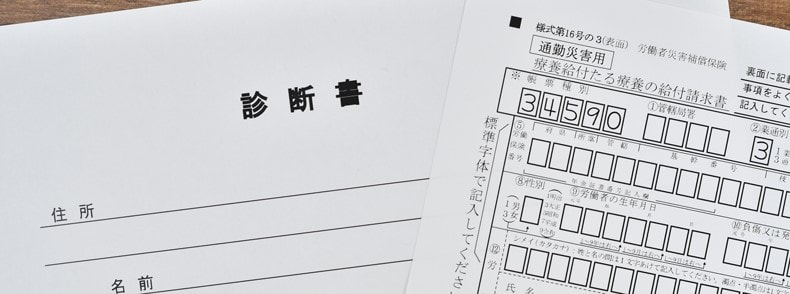従業員への安全配慮に対するリスクファイナンス
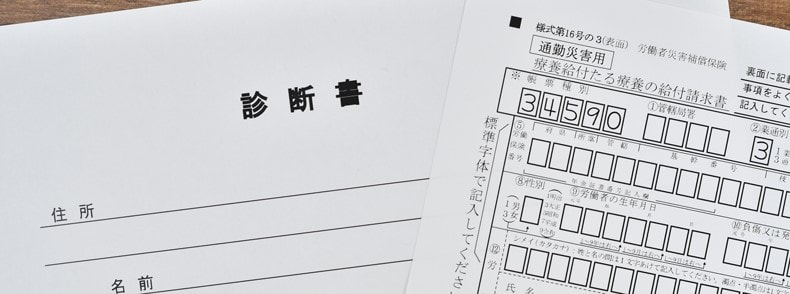
- 目次
-
1. はじめに
-
2. 業務災害補償制度の内容について
-
3. 最後に
1. はじめに
前回のコラムでは、事業全般のリスクを補償するビジネス総合保険制度についてご説明しました。
今回のコラムでは商工三団体が提供する中小企業向け損害保険のパッケージ商品のうち、業務災害補償制度についてご説明します。さらに次回のコラムでは休業補償制度についてご説明します。
まず始めに昨今の企業を取り巻く労災事故の現状と企業に求められている責任について3点ご説明します。
企業を取り巻く労働環境の変化
1. 安全配慮義務
使用者は、従業員の労働上の安全に関して必要な配慮をする義務があります。
2. ハラスメントの防止
パワハラ防止法によるパワハラに対する防止措置が義務化されます。
また、従業員の意識も高まっています。
3. 労災事故の多様化・高額化
ケガ系の労災事故だけでなく、過労死による労災事故も増加傾向にあります。
賠償金額も高額化する傾向があります。
2008年に労働契約法に明文化された「安全配慮義務」や2020年に施行されたパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)など、企業に求められる従業員の労働環境への配慮がますます重要となっています。
「安全配慮義務」とは、使用者(雇い主)が、従業員の労働上の安全に対して必要な配慮をしなければならいという義務を指します。
また、パワハラ防止法では、中小企業においても2022年4月より企業がパワハラに対して雇用管理上必要な防止措置を講じることが義務化されます。ハラスメントが認識されるにつれ、被害者が声を上げやすい環境が醸成されていることから、企業として労務リスクに関する備えはますます必要となっていると言われています。
このような企業に求められる責任の高まりは、訴訟に至った場合の賠償額にも表れています。昭和における労災事故はケガ系の事故が大半を占めていましたが、近年は過労死に関する労災事故が多くなっており、過労死してしまった従業員の遺族が企業に対して1億円以上の賠償を求める訴訟に発展するケースもあります。
安全な労働環境をより高いレベルで求められる世の中になっているため、労働環境の管理を怠った場合に企業が問われる管理責任は重くなっています。
 (ご参考)
(ご参考)
2. 業務災害補償制度の内容について
このような企業が抱える労務リスクに対して補償をご提供できるのが業務災害補償制度です。業務災害補償制度は従業員が被った業務上の災害について、企業に発生する様々な損害を補償します。
本制度は大きく3つの補償から成り立っています。従業員の労災上乗せ補償、従業員等との労務トラブルに関する企業のための補償、補償の範囲を拡大するためのオプション補償です。
業務災害補償制度の補償内容
補償1
従業員の労災上乗せ補償
補償2
従業員等との労務トラブルに関する企業のための補償
補償3
補償の範囲を拡大するためのオプション補償
(1)従業員の労災上乗せ補償
1つ目の補償である従業員の労災上乗せ補償についてご説明します。
本補償により、従業員等が業務に従事中、もしくは通勤中に被った身体障害について、企業が、政府労災に上乗せして、法定外補償として死亡・後遺障害補償保険金や入院・手術補償保険金、通院補償保険金を受け取ることができます。法定外補償とは、政府労災保険金とは別に、企業が従業員に対して労働協約等により災害補償を行う補償を指します。
本補償により、企業は従業員に対して万が一の補償を政府の基準以上に用意していることをアピールできることに加え、大事故により政府労災ではまかないきれない可能性がある従業員の損害に備えることが可能となります。
労災上乗せ補償の特徴
ポイント1
政府労災の給付を待たずに保険金を受け取れます。
ポイント2
ケガだけでなく、食中毒等も補償の対象です。
ポイント3
労災認定の場合、精神疾患や脳疾患などの疾病も補償の対象です。
(2)従業員等との労務トラブルに関する企業のための補償
2つ目の補償である労災に関する企業のための補償についてご説明します。
冒頭でもご説明したとおり、労災に関する賠償責任を従業員から企業に問われることが多くなっていることを踏まえ、企業をお守りする各種補償が用意されています。
主な補償は2つです。
1つ目は「使用者賠償責任補償」です。
本補償では、従業員が業務上の事由または通勤により被った身体障害について、企業・役員が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を受け取れます。安全配慮義務違反などによって従業員から訴訟を起こされた場合、労働環境に落ち度がなかったことを立証しなければならないのは企業であり、実務上立証することが困難と言われています。
そのため、従業員から訴訟を受け、示談金や賠償金をお支払いする事例は多く、政府労災だけで賄うことが困難な賠償責任額となる可能性もあり、そのようなケースでご活用いただける補償となります。
2つ目は「雇用関連賠償責任補償」です。
本補償は、パワハラ・セクハラ・マタハラ行為に対する管理責任や不当解雇などにより、企業や役員が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を受け取れます。冒頭でご説明したパワハラ防止法を始め、パワハラ等に関する世間の目は厳しさを増す一方で、被害者が声を上げやすい環境が整っています。
そのため企業は今まで以上に管理責任が問われやすい環境となっています。また、実際に数百万円の損害賠償を認められた事例も存在します。
本特約ではそのようなパワハラ等と認定される管理責任や不当解雇等で訴えられた企業の賠償責任を補償します。
賠償責任に関する補償
使用者賠償責任補償
従業員が業務上の事由または通勤により被った身体障害について、企業・役員が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害が補償の対象となります。
雇用関連賠償責任補償
パワハラやセクハラ等の管理責任や不当解雇により、企業や役員が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害が補償の対象となります。
(3)補償の範囲を拡大するためのオプション補償
3つ目の補償であるオプション補償についてご説明します。
3. 最後に
健康経営アシストサービスの例
ストレスチェックサービス
WEB上で従業員の皆様のストレスチェックを実施し、チェック結果を個人宛にフィードバックします。また、事業者様には集団的分析の結果をご提供します。
メンタルケア・ホットライン
「メンタル面が原因の休職・退職が増えてきた、うつ病で悩んでいる従業員がいる」、といったお悩み・ご相談にお応えします。
(ご注意)
本コラムはリスクファイナンスの一般的な方法について記載したコラムであり、保険募集文書ではございません。
関連記事