平時の技術協力や営業での提携で、有事の事業継続を強固なものに“平時にこそ企業の役に立つ「連携型ジギョケイ」の作り方”

ユーアイ精機株式会社
有限会社ハチスカテクノ
有事を見据えた連携は、事業継続に大きな力となる。その連携が、日常の事業活動にも利するものであれば、両社の関係性はより強くなる。互いの理想が合致したユーアイ精機とハチスカテクノは、連携型事業継続力強化計画を入口に、業績向上を目指す。
「事業の継続」「高い技術力の獲得」を目指し連携
ユーアイ精機とハチスカテクノは、ともに愛知県に本拠を構え、製造業を営んでいます。
「当社の業務の主軸は、自動車用の試作部品の金型製作です。部品メーカーが製品を作る前段階の工程になります。」(水野氏)
「当社の業務の主軸は、自動車用の試作部品の金型製作です。部品メーカーが製品を作る前段階の工程になります。」(水野氏)
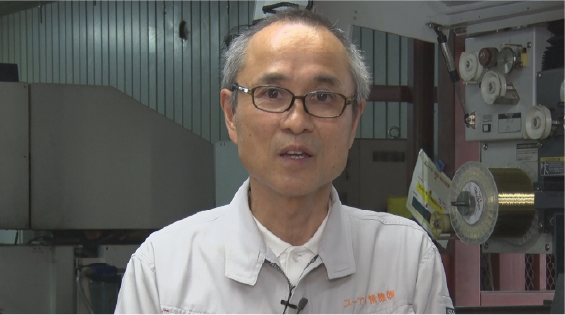
「当社は金型製作会社として創業しましたが、その後、電流を流したワイヤー線で金属を切断加工する『ワイヤーカット』を専業とするようになりました。現在は独自に磨いた技術を武器に、自社でワイヤー加工部門を持たない会社さま、高精度が求められる加工部品が必要な会社さまなどと、お取り引きしています」(蜂須賀氏)
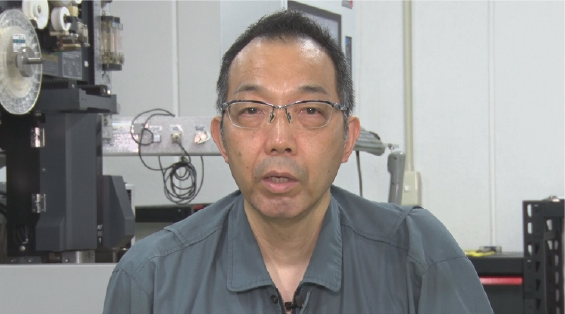
両社は連携の前に、それぞれ単独での事業継続力強化計画を策定していました。
「ある異業種交流会で、東日本大震災で被災した方から『サプライチェーンのうち1社の事業が止まるだけで、大きな影響が出てしまった』という経験談を伺いました。実は当社は津波で浸水する可能性がある地域に立地しており、被災により事業継続が困難になる可能性があったのです。そうした時にお取引先さまにご迷惑をかけることを極力避けるため、まず単独型での事業継続力強化計画が必要だと考えました。その後のコロナ禍で、天災以外の事業継続リスクにも対応すべきとの考えから、連携型の重要性を意識するようになりました」(蜂須賀氏)
「当社の場合は、お付き合いのあった保険会社からおすすめをいただいたのが、事業継続力強化計画策定のきっかけです。そのときは『保険会社がいろいろやってくれるから』くらいの意識でした。その後、ハチスカテクノさんとは同じお取引先があった関係で知り合い、連携のお誘いをいただいたという流れです。もしこの機会がなければ、単独型の事業継続力強化計画を“作りっぱなし”になっていただけかもしれません」(水野氏)
蜂須賀氏がコロナ禍で連携型を重要視するようになったのは、外部環境を含めた自社の状況を鑑みてのことでした。
「高い技術を持っていても、その規模の小ささゆえ、ちょっとした外部要因で廃業する企業は少なくありません。私はそうした廃業で貴重な技術が失われてしまうケースを数多く見てきました。当社も従業員数10名に足りない零細企業ですから、そうした“廃業の危機”とは無縁ではいられないと思うようになりました。そこで“万一のときの提携先”を探しているうちに、ユーアイ精機さんをご紹介いただいたのです」(蜂須賀氏)
一方、水野氏にとっては、より技術力を高め、事業を拡大することが大きな課題となっていました。
「当社でもワイヤー加工を手がけており、一部はハチスカテクノさんと同じ機械を使っています。しかし色々と工夫してみたのですが、ハチスカテクノさんが実現している高い精度が出せないのです。技術力を向上させ、競争力を高めるには、その秘訣をうかがわなければならないと思いました」(水野氏)
この水野氏の要望は、いざというときの代替生産先、さらには技術の伝承先を探していた蜂須賀氏にとって、渡りに船でした。
「そもそも私は、自社だけで技術を抱えるというつもりはないんです。当社のような小さな会社では、どんなに高い技術を持っていても、お仕事の範囲は限られています。であれば、信頼できるところにその技術を公開して、互いに売上げを伸ばすことができたらいい、そう考えていたのです」(蜂須賀氏)
こうして両社は、連携型事業継続力強化計画を策定することになったのです。
「ある異業種交流会で、東日本大震災で被災した方から『サプライチェーンのうち1社の事業が止まるだけで、大きな影響が出てしまった』という経験談を伺いました。実は当社は津波で浸水する可能性がある地域に立地しており、被災により事業継続が困難になる可能性があったのです。そうした時にお取引先さまにご迷惑をかけることを極力避けるため、まず単独型での事業継続力強化計画が必要だと考えました。その後のコロナ禍で、天災以外の事業継続リスクにも対応すべきとの考えから、連携型の重要性を意識するようになりました」(蜂須賀氏)
「当社の場合は、お付き合いのあった保険会社からおすすめをいただいたのが、事業継続力強化計画策定のきっかけです。そのときは『保険会社がいろいろやってくれるから』くらいの意識でした。その後、ハチスカテクノさんとは同じお取引先があった関係で知り合い、連携のお誘いをいただいたという流れです。もしこの機会がなければ、単独型の事業継続力強化計画を“作りっぱなし”になっていただけかもしれません」(水野氏)
蜂須賀氏がコロナ禍で連携型を重要視するようになったのは、外部環境を含めた自社の状況を鑑みてのことでした。
「高い技術を持っていても、その規模の小ささゆえ、ちょっとした外部要因で廃業する企業は少なくありません。私はそうした廃業で貴重な技術が失われてしまうケースを数多く見てきました。当社も従業員数10名に足りない零細企業ですから、そうした“廃業の危機”とは無縁ではいられないと思うようになりました。そこで“万一のときの提携先”を探しているうちに、ユーアイ精機さんをご紹介いただいたのです」(蜂須賀氏)
一方、水野氏にとっては、より技術力を高め、事業を拡大することが大きな課題となっていました。
「当社でもワイヤー加工を手がけており、一部はハチスカテクノさんと同じ機械を使っています。しかし色々と工夫してみたのですが、ハチスカテクノさんが実現している高い精度が出せないのです。技術力を向上させ、競争力を高めるには、その秘訣をうかがわなければならないと思いました」(水野氏)
この水野氏の要望は、いざというときの代替生産先、さらには技術の伝承先を探していた蜂須賀氏にとって、渡りに船でした。
「そもそも私は、自社だけで技術を抱えるというつもりはないんです。当社のような小さな会社では、どんなに高い技術を持っていても、お仕事の範囲は限られています。であれば、信頼できるところにその技術を公開して、互いに売上げを伸ばすことができたらいい、そう考えていたのです」(蜂須賀氏)
こうして両社は、連携型事業継続力強化計画を策定することになったのです。
月イチのミーティングで課題感を共有、人的交流の段階へ

では、現状では、両社はどういった協力関係になっているのでしょうか。
「現在は私と水野さん、経営トップ同士が月に1回リモートミーティングを行い、お互いの課題把握、技術移転の具体的な方法、さらにお取引先情報の交換など業績向上につながる内容について、お打ち合わせしています。当面の課題として考えているのは、技術移転を具体的にどう行うか、です」(蜂須賀氏)
「トップ同士であれば、腹を割って深い話ができます。細かい技術の内容についても、信頼関係のもと、隠すことなく互いに開示できます。ただその内容を現場レベルまで下ろしたときに、どこまで、またどうやって機密保持を行うかというところについては、これから詰めていかなければならない話だと思っています」(水野氏)
ただ、技術移転の手法については、かなり話が進んでいるということです。
「両社で同じものを、同じ速度とクオリティで作れるというのがゴールになります。そのため、加工情報の保管方法など、実作業の前提条件となる部分をまず共通化していく方向で動いています。ここが片付いた上で、実際のワイヤーカットの技術協力に進む方向です。たとえば同じ機械を使い、同じ手順でやっても、担当者が異なると同じ精度の製品ができない、同じ生産性が実現できないということがよくあります。これはものづくりに携わったことがある人ならご理解いただけるでしょう。当社とハチスカテクノさんも同様で、ハチスカテクノさんでできることが、当社ではできない状況なのです。この『なぜ当社でできないのか』については、実際の人の交流がなければ解決できない課題だと思っています」(水野氏)
「具体的には、当社で定年になった人材をユーアイ精機さんに派遣し、同じ機械を使ってのものづくりで、技術を伝承するというものです。さきほどの『どうやって機密保持するか』という課題はありますが、これをクリアして、できるだけ早く実現したいですね」(蜂須賀氏)
「現在は私と水野さん、経営トップ同士が月に1回リモートミーティングを行い、お互いの課題把握、技術移転の具体的な方法、さらにお取引先情報の交換など業績向上につながる内容について、お打ち合わせしています。当面の課題として考えているのは、技術移転を具体的にどう行うか、です」(蜂須賀氏)
「トップ同士であれば、腹を割って深い話ができます。細かい技術の内容についても、信頼関係のもと、隠すことなく互いに開示できます。ただその内容を現場レベルまで下ろしたときに、どこまで、またどうやって機密保持を行うかというところについては、これから詰めていかなければならない話だと思っています」(水野氏)
ただ、技術移転の手法については、かなり話が進んでいるということです。
「両社で同じものを、同じ速度とクオリティで作れるというのがゴールになります。そのため、加工情報の保管方法など、実作業の前提条件となる部分をまず共通化していく方向で動いています。ここが片付いた上で、実際のワイヤーカットの技術協力に進む方向です。たとえば同じ機械を使い、同じ手順でやっても、担当者が異なると同じ精度の製品ができない、同じ生産性が実現できないということがよくあります。これはものづくりに携わったことがある人ならご理解いただけるでしょう。当社とハチスカテクノさんも同様で、ハチスカテクノさんでできることが、当社ではできない状況なのです。この『なぜ当社でできないのか』については、実際の人の交流がなければ解決できない課題だと思っています」(水野氏)
「具体的には、当社で定年になった人材をユーアイ精機さんに派遣し、同じ機械を使ってのものづくりで、技術を伝承するというものです。さきほどの『どうやって機密保持するか』という課題はありますが、これをクリアして、できるだけ早く実現したいですね」(蜂須賀氏)

ユーアイ精機株式会社と有限会社ハチスカテクノの連携型事業計画
一部抜粋(両社のご協力のもと掲載)
| 自然災害等が発生した場合における対応手順 | |
|---|---|
| 全ての連携業者が、従業員及び顧客等の避難に関する手順を取り決めている。 | |
| 地震・水害 |
|
| 感染症 |
|
| 全ての連携業者が、従業員等の安否確認を行う手順を取り決めている。 | |
|
地震・水害・感染症
|
|
| 連携事業者間で、自然災害等が発生した場合における指揮命令体制が整備されている。 | |
連携業者間における協力体制については、以下の状況となったときに、平時からの技術連携会議を災害時対応会議に格上げすることとしている。
|
|
| 連携事業者間で、被害状況を把握し、被害情報について情報発信をする手順が共有されている。 | |
|
|
連携事業者それぞれの役割(連携事業者間で、自然災害等発生時における指揮命令体制)
|
|
| 自然災害等が発生した場合における人員体制の整備 |
|---|
| 対策及び取組内容 |
|
| 連携事業者それぞれの役割 |
|
| 連携事業継続力強化に資する設備、機器及び装置の導入 |
|---|
| 対策及び取組内容 |
|
| 連携事業者それぞれの役割 |
|
| 事業活動を継続するための資金の調達手段の確保 |
|---|
| 対策及び取組内容 |
|
| 連携事業者それぞれの役割 |
|
| 事業活動を継続するための重要情報の保護 |
|---|
| 対策及び取組内容 |
|
| 連携事業者それぞれの役割 |
|
「有事を見据えた連携」を入口に、ともに業績を伸ばせる関係を
水野氏、蜂須賀氏とも意識を同じくするのが、「有事だけを考えた連携では、うまく続かないのではないか」ということです。
「『有事の際に連携してやっていきましょう』というのは、美しい関係ですが、それだけではなかなかハードルが高いと思います。そもそも、いざ有事のときに同じものを作ることができるか、さらには同じものを作れたとしても、同じ生産性を確保できるかということです。もし生産性に劣る部分があれば、それだけ利益が少なくなり、支援そのものが難しくなるからです。それよりも、平時でも技術交流や営業情報の交換で関係を深め、同じ製品が同じ生産性で作れるような技術を磨くことで売上げを伸ばしていけば、お互いを“欠かせないパートナー”として認識できるようになるでしょう。そうなれば有事の助け合いは、普段の協力関係の延長線上で、自然にできるようになるはずです」(水野氏)
「『有事の際に連携してやっていきましょう』というのは、美しい関係ですが、それだけではなかなかハードルが高いと思います。そもそも、いざ有事のときに同じものを作ることができるか、さらには同じものを作れたとしても、同じ生産性を確保できるかということです。もし生産性に劣る部分があれば、それだけ利益が少なくなり、支援そのものが難しくなるからです。それよりも、平時でも技術交流や営業情報の交換で関係を深め、同じ製品が同じ生産性で作れるような技術を磨くことで売上げを伸ばしていけば、お互いを“欠かせないパートナー”として認識できるようになるでしょう。そうなれば有事の助け合いは、普段の協力関係の延長線上で、自然にできるようになるはずです」(水野氏)

2社連携による技術力の研鑽・向上と生産性の向上についてアピール。
「繰り返しになりますが、私たちのような小さな会社は、何か強みを持っていても、その強みだけでずっと存続できるわけじゃないと思っています。いい仲間を見つけて、強いところは鍛えて伸ばし、弱いところは互いに助け合うような関係性を築いていけば、企業としての体力は強くなるし、お客さんからの信用度も上がると思うんです」(蜂須賀氏)
ただ、そうした関係を“赤の他人”である他企業といきなり築くのは困難です。
「そのとっかかりに、連携型事業継続力強化計画は最適だと思います。当社も、課題感を持って連携先を探していたハチスカテクノさんと、連携型事業継続力強化計画を知り合い、そこから現在の関係性につながりました。いまは互いに頑張って、互いに売上げを上げようというのが合い言葉になっています」(水野氏)
「連携の相手先を増やせば増やすほど、自社の体力は上がり、業績向上の可能性もどんどん高くなると思います。当社はいまも、事業継続をキーワードに、新たな連携先を探しています」(蜂須賀氏)
ただ、そうした関係を“赤の他人”である他企業といきなり築くのは困難です。
「そのとっかかりに、連携型事業継続力強化計画は最適だと思います。当社も、課題感を持って連携先を探していたハチスカテクノさんと、連携型事業継続力強化計画を知り合い、そこから現在の関係性につながりました。いまは互いに頑張って、互いに売上げを上げようというのが合い言葉になっています」(水野氏)
「連携の相手先を増やせば増やすほど、自社の体力は上がり、業績向上の可能性もどんどん高くなると思います。当社はいまも、事業継続をキーワードに、新たな連携先を探しています」(蜂須賀氏)
専門家のコメント
有事にしか使わないジギョケイでは長続きしません。今回の事例は毎月1回の社長も参加するオンラインミーティングを通じて、お互いの課題や取引先情報を交換し、平時から共同で営業して、売り上げ拡大と経営改善に結び付けているのがポイントです。
連携型ジギョケイを実行するには、代替生産が本当にできるのか技術情報の見える化が大切であり、品質と価格の確認をされています。
連携型ジギョケイで中小企業が弱いところをカバーしあうことは大切ですが、平時でもお互いが利益を生む連携型ジギョケイが理想であり、それを実践されている素晴らしい事例です。
連携型ジギョケイを実行するには、代替生産が本当にできるのか技術情報の見える化が大切であり、品質と価格の確認をされています。
連携型ジギョケイで中小企業が弱いところをカバーしあうことは大切ですが、平時でもお互いが利益を生む連携型ジギョケイが理想であり、それを実践されている素晴らしい事例です。
SOMPOリスクマネジメント株式会社 エグゼクティブコンサルタント
高橋 孝一 氏
横浜国立大学工学部化学工学科卒業後、1980年に保険会社入社、44年間、企業のリスクマネジメントを専門に歩み、『リスク管理体制構築支援』、『火災・爆発・風水害などの事故防止』、『製造物責任対策』、『事業継続マネジメント(BCM)』、『海外危機管理対策』、『コンプライアンス』などのコンサルティングの提供やリスクマネジメントセミナーの講師等で活動中
◆主な資格・社外団体役職
NPO 事業継続推進機構
文化庁美術品保証制度部会専門調査会会長
◆官庁・経団連等で有識者として参画している委員会
内閣府 :2005年から「事業継続ガイドライン」の策定に参画
中小企業庁:2005年から「事業継続ガイドライン」の策定に参画
:2018年から「中小企業強靭化研究会」委員
経済産業省:2016年から「地域連携BCP普及検討会」委員
高橋 孝一 氏
横浜国立大学工学部化学工学科卒業後、1980年に保険会社入社、44年間、企業のリスクマネジメントを専門に歩み、『リスク管理体制構築支援』、『火災・爆発・風水害などの事故防止』、『製造物責任対策』、『事業継続マネジメント(BCM)』、『海外危機管理対策』、『コンプライアンス』などのコンサルティングの提供やリスクマネジメントセミナーの講師等で活動中
◆主な資格・社外団体役職
NPO 事業継続推進機構
文化庁美術品保証制度部会専門調査会会長
◆官庁・経団連等で有識者として参画している委員会
内閣府 :2005年から「事業継続ガイドライン」の策定に参画
中小企業庁:2005年から「事業継続ガイドライン」の策定に参画
:2018年から「中小企業強靭化研究会」委員
経済産業省:2016年から「地域連携BCP普及検討会」委員


