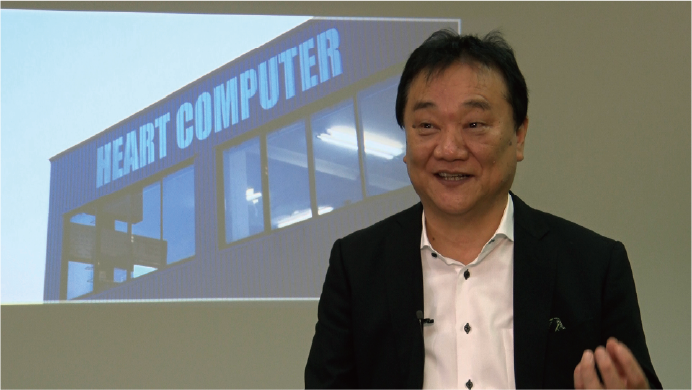連携型ジギョケイのおかげで落ち着けた。~災害を想定外で済まさないために~

株式会社ハートコンピューター
製造管理システム、販売管理システムなど、ITの力で日本の酒造メーカーの約半数の酒造りを支える「ハートコンピューター」は、防火責任者に選任された総務部社員の発案から、BCPへの取り組みに着手。中小機構近畿本部の支援により、短時間で連携型ジギョケイを策定した。
インタビュー(9分7秒)
“酒造り”のIT化にチャンスを見出し、大きく成長
滋賀県東北部、琵琶湖に面した長浜市は、東の伊吹山系から流れる姉川や、北の福井県境の山々に源を持つ余呉川、高時川が作り出した平野を中心に、11万3000人が暮らす都市圏が形成されています。
ハートコンピューターは、この地で生まれ育った平井正公代表が創業したソフトウェアメーカーで、酒造メーカー向け製造管理、販売管理ソフトウェアで国内トップのシェアを持っています。
「30才のころ、電気店を営む実家で、当時黎明期だったPCを売るためにソフトウェアの勉強をはじめました。地域のお客さまの依頼を受け小さなアプリケーションソフトを作っていましたが、売り上げの見込める規模のものはすでにシステム開発会社ががっちりと食い込んでいて、新たなお取り引きが難しい状態でした。また依頼を受けてさまざまなソフトウェア開発する仕事そのものに面白さを感じていましたが、分野が絞れないため、知見も深くはならない状態でした」(平井氏)
そこで平井氏は、まだシステム開発会社が入り込んでいない業種にターゲットを絞り、事業の拡大を目指すことを考えました。
そして平井氏が最終的に選択したのが「酒造り」の業界でした。
「日本酒の酒造りにおける酒税の計算方式がいい意味で複雑で、非常によくできていることを知りました。計算式そのものは明治時代の大蔵官僚が作ったものですが、製造工程から製品になるまで、きちんと数学的に計算できるものになっている。ここをシステム化すれば、大幅な省力化につながり、日本酒メーカーからは歓迎されるだろうと。そして日本酒メーカーは全国津々浦々にあり、文化の一部となっています。取引先に事欠かないだけでなく、その地域の文化を側面から支えるという、社会貢献的な意味もあると考えました」(平井氏)
この平井氏の判断は的確で、昭和61年に地元の酒造協業組合から製造および販売管理システムの開発を受託。法人化後の平成元年には、アプリケーションパッケージの販売を開始します。創業から36年経った現在、同社は日本酒メーカーだけでなく、ビールや焼酎、ワインなど、国内の酒造メーカーのほぼ半分を得意先とするシステム開発会社へと成長しました。
中小機構近畿本部の支援を受け、ジギョケイ策定を本格化
そんな同社のジギョケイ策定への取り組みは、総務部の社員、千葉彩香氏が防火管理責任者に選ばれたことをきっかけに、はじまりました。
ジギョケイについて内容を確認した千葉氏は、このマークを取得で同社の信頼性がより高まるのではないかと考え、さっそく行動に移します。
「中小企業庁のサイトにある「作り方ガイド(策定の手引き)」を参考に、まずは自分たちだけで策定に取り組みました。ただこうした作業に慣れていなかったこともあり、なかなか前に進めませんでした。そこで考えをあらため、ジギョケイ策定に向けての支援を受けるため、中小機構近畿本部に問い合わせました。するとすぐにBCPに詳しい専門家など複数名がいらっしゃって、不明な点も少しずつ分かってくるようになりました。当初は単独型での申請を考えていましたが、グループ会社があることを伝えると、より強固な連携型はどうかと案内していただきました。社内でも話し合った末、連携型ジギョケイの策定をすることになり、ご支援いただけることになりました。」(千葉氏)
そしてこの支援により、千葉氏は「なぜ自分たちだけでうまく策定できなかったのか」を知ることになります。
「ジギョケイには、『どんな災害が想定されるか、その災害にどう対応するか』など、まとめなければならない項目が数多くありますが、そこをどう作ればいいかわからない状態でした。しかし専門家の支援により具体化されたジギョケイには『いままで自分たちが当たり前に考え、やってきたこと』がわかりやすく記されていました。つまり、自分たちだけではうまく言語化できなかった『頭の中にあるけれど、ちゃんと整理できていなかったもの』が、専門家の支援のおかげで分かりやすくなっていきました。」(千葉氏)
想定されるリスク:地震・水害
リスク発生による影響
- 今後30年以内に震度5弱の地震が発生する可能性が79.0%。津波による浸水深は0.5m未満となっている。
- 地震により一部の連携事業者で事務所、事業所の倒壊の可能性がある。
- 災害により一部の連携事業者において、運転資金や復旧資金の確保が困難となる可能性がある。
- 通信の途絶、被災等により外部サーバー、オフィス内のサーバーが利用できなくなり、事業活動に必要な情報の入手が困難になる可能性がある。
対応策と効果
- ハートコンピューターでは「長浜市総合防災マップ」、独自の「避難誘導マップ」を従業員入口に掲示する。
- 従業員全員に防災用ヘルメットを配布し、社外での被災時の行動基準を取り決めている。
- 安否について、LINEおよびLINE WORKSと防災専用ダイヤルで報告するよう周知している。
- 連携事業者間で平時より月1回の連絡会議を開催、発災時には災害対策会議に格上げする。
- 震度5弱以上の地震が発生したときは災害対策会議で状況を把握し、顧客や行政に発信する。
- 被災連携事業者の復旧を支援するため、ハートコンピューターが中心となって、必要に応じ人員を提供する等の調整を行う。
想定されるリスク:感染症
リスク発生による影響
- 国内で感染症発生が確認された場合は、一部の連携事業者において、移動の制限や行政からの外出自粛要請等により、店舗等における必要な人員が確保できなくなる可能性がある。
- 感染症が拡大し、社員本人または家族が感染した場合は、長期間出勤できなくなる従業員が複数発生する可能性がある。
- 事業活動に与える影響としては、顧客情報や業務の引継ぎが滞る、営業等の停止の検討により顧客に迷惑がかかることなどが想定される。
- 感染拡大を防止するための設備、備品等を用意するためのコストが想定され、営業活動が一時的に停止すること等が想定される。
- 外出自粛が長期化すれば、運転資金が逼迫する。
対応策と効果
- 国内で感染症発生が確認された場合は、ハートコンピューターでは消毒が必要と考えられるオフィスおよび設備に消毒や従業員の手洗いをはじめとする感染症対策の徹底を図る。
- 体調不良の従業員の出勤停止規定の整備、従業員やその家族における出勤前の検温の励行を実施する。
- 連携事業者内で、消毒衛生用品を融通する。
- 連携体での資金融通や国や自治体の金融支援についてグループ内に共有する。
大雨で地域が洪水被害に遭うなか、冷静な対応を実施
同社が近畿本部へジギョケイについて問い合わせたのは令和4年5月で、6月下旬に行われた初回打ち合わせから数日後には計画がまとまり、申請を実施。7月下旬に認定を受けることになりました。
「そもそも自分たちだけではできなかったことが、専門家のサポートによりこれほどまでのスピードで認定が受けられることになり、本当にうれしく、また心強く思いました」(千葉氏)
そしてこのジギョケイが役立つ事態が、申請直後に発生しました。
「令和4年8月、大雨がこの地域を襲い、当社の2kmほど東側を南北に流れる高時川で氾濫が発生したんです。自分の地元地域でしたが、これまで水害に遭うなんてことはなく、びっくりしました」(平井氏)
「1時間に90mmという猛烈な雨で、記録的短時間大雨情報も発令されるほどでした。川に近い地域では床上、床下浸水も発生し、6000人以上に避難指示が出ました。氾濫の第一報が入ったのは始業して間もないタイミングで、状況がどうなるかわからないなか、どう対応するか、判断を迫られました」(千葉氏)
しかしここで、策定したばかりのジギョケイが効果を発揮することになります。
「ジギョケイにより、自然災害が発生したときの情報収集の方法や社内にどう周知するか、そしてどう対処するかをきちんと文書化していたことで、社内の意思の共有とスムーズな対応ができました。具体的には、万一に備えて配布している防災ヘルメットを各自が着用し、安否についてはLINEおよびLINE WORKSなどで確認、被害状況は連携各社で共有、避難が必要な場合は従業員入口に掲示した長浜市の『総合防災マップ』、当社が独自に作成した『避難誘導マップ』をもとに避難するというものです。今回は幸いにも社屋まで洪水が到達することはありませんでしたが、ジギョケイ策定の効果を大きく実感した出来事でした」(千葉氏)
自社の知見と経験を活かし、業界全体の事業継続力向上を推進
さらにこの実体験を受け、同社はジギョケイの運用について、見直しを進めることも検討しています。
最後に平井氏に、事業継続にかける思いをうかがいました。
関連記事