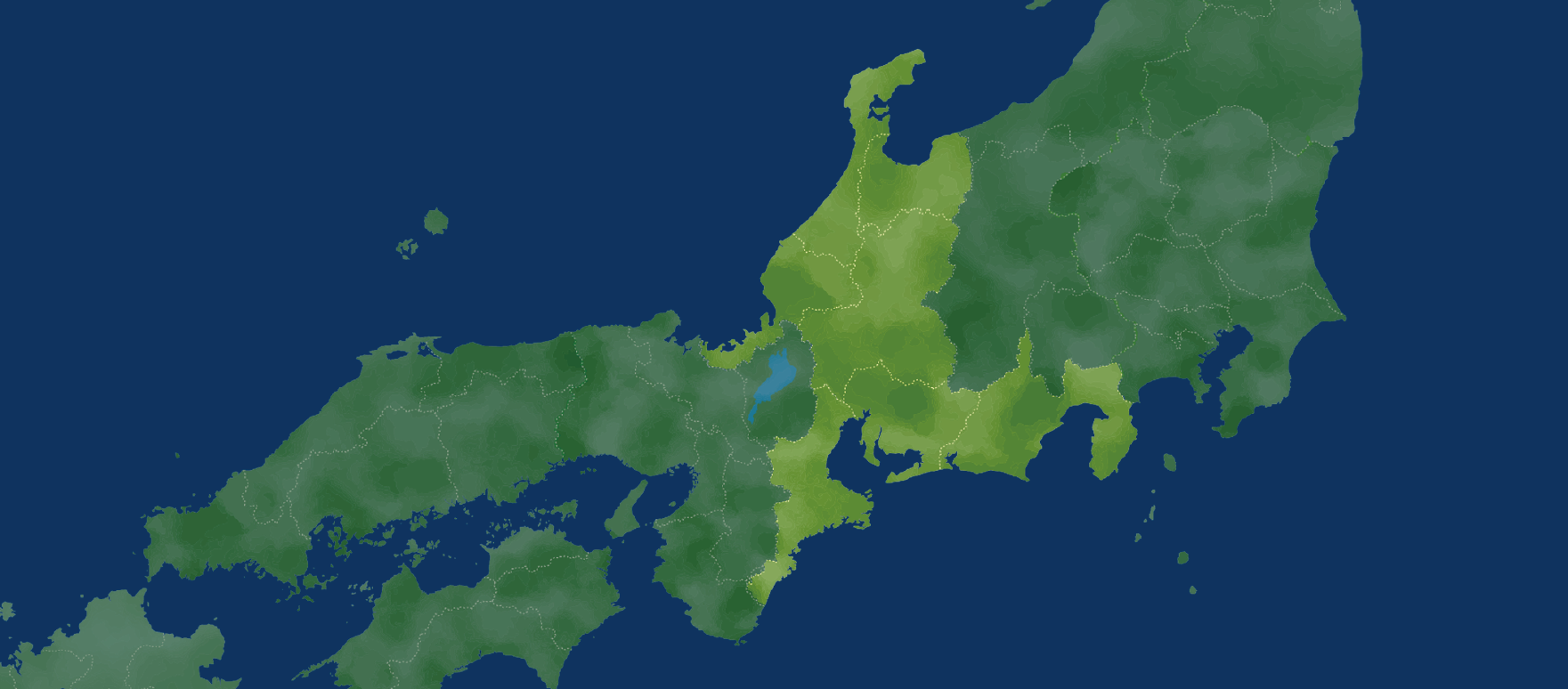商業施設が連携し災害対策を強化

福井県共同店舗協同組合連合会
- 代表理事
- 竹内 邦夫
- 業種
- 協同組合
- 所在地
- 福井県福井市大和田2丁目1212番地
- 組合員数
- 9名
福井県内でショッピングセンターやショッピングモールを運営する8つの事業協同組合と1つの株式会社で構成され、組合員同士の情報交換やスキルアップを目的に平成8年11月に設立された協同組合連合会。 協同組合事務局で新型コロナウイルス感染が拡大、業務が停止したことを機に、地震や大雪による罹災、感染症拡大を想定した事業継続計画を立案。大規模災害発生時には地域の生活を守る避難所としても機能する仕組みを整えた。
インタビュー(7分10秒)
独自の「福井方式」でショッピングモールを運営
今回ご紹介するのは、既存の協同組合連合会を基盤として、福井県内の9つのショッピングモールが広域で連携し、認定を取得した事例です。
ショッピングモールは通常、デベロッパーが主体となって開発し、テナントを募集し運営することが一般的です。しかし福井県では、地元の事業者が協同組合を設立し、商業施設を開発、運営する「福井方式」と呼ばれる形式を採用しています。
「この福井方式は約50年前にスタートしたと聞いています。こうした方式は県内各地に広がりましたが、どうしても地元の事業者による運営のため、それぞれの組合は規模も小さく、情報も限られていました。そこでこうした組合を束ねる組織をつくり、お互いに情報交換し、協力してスキルアップ、レベルアップしていこうという趣旨で設立されたのが、『福井県共同店舗協同組合連合会(以下、連合会)』なのです」(竹内氏)
現在、連合会には、福井県内の8つの事業協同組合と1つの株式会社が加盟しています。
「連合会と協同組合は上下の関係ではなく、互いに助け合い連携する関係です。連合会は収益事業として、商品券の販売と回収を行い、手数料を得ています。しかしこの収益は内部留保するためのものではなく、事務局の運営費用、福井県中小企業団体中央会(以下、中央会)や中小機構が主催する勉強会に組合員のみなさんを派遣するための費用などに充てており、余剰が出た場合はいただいた会費の一部をお返しすることも行っています」(竹内氏)
コロナ禍による施設休業と地震被害が策定の契機に
この連合会が、事業継続力強化計画を策定することになったきっかけは、コロナ禍による組合員事務局および商業施設の休業でした。
「ある組合員の事務局で多くのスタッフが新型コロナウイルスに感染し、業務ができなくなったのです。商業施設そのものも、半月ほどの休業を余儀なくされました」(竹内氏)
さらに2020年9月には、最大震度5弱の地震が福井県を襲います。
「一部の商業施設で、建物が被災しました。休業するほどの被害ではなかったことが、不幸中の幸いでした」(竹内氏)
このコロナ禍と天災を経験した竹内氏の心に浮かんだのは、すでに自身が理事長を務める「協同組合福井ショッピングモール(愛称:Lpa、エルパ)(以下、Lpa)」で策定していた事業継続力強化計画を、連合会でも活用できないかということでした。
「2020年にLpaで『ものづくり補助金』の申請に取り組んでいたとき、加点項目に事業継続力強化計画が含まれていることを知りました。加点をぜひとも得たいと思い、中央会、中小機構の支援を仰ぎつつ、Lpaとして計画策定を行ったのです」(竹内氏)
コロナ禍や地震による被災は、決して大きな組織ではない組合員が単独で対応するには難しい課題です。竹内氏は、連合会として事業継続力強化計画を策定し、組合員同士で助け合う仕組みがあれば、そうした課題に立ち向かうことがより容易になると考えたのです。
「コロナ感染が拡大した事務局は、どうすればいいのかと途方に暮れたはずです。実際、どの組合員も同じ状況になるでしょう。であれば、そもそも情報交換を目的に生まれた連合会が、そうしたコロナ対応、さらには天災対応のノウハウを共有し、お互いに助け合うことができれば、被害を最小限に食い止めることができるのではないかと考えました。そこで中央会、中小機構に相談にうかがったところ、策定に向けての支援を快く引き受けてくれました」(竹内氏)
想定されるリスク:地震
リスク発生による影響
- 営業中に被災した場合、設備の落下、避難中の転倒などによりケガ人が発生する
- 夜間に発生した場合、翌営業日の従業員確保が難しくなり営業不能が想定される
- 配管等が破損した場合は復旧が長期化することが想定される
- 事業所内サーバーの破損で重要データが喪失すると、事業継続が難しくなる
対応策と効果
- 組合員ごとに避難場所を定め、避難ルートを策定する
- 共同店舗は共同店舗構成者の連絡先リストを作成し、メール、SNS、電話で安否確認する
- 連合会、被災共同店舗はそれぞれ災害対策本部を設置し、情報収集、発信を行う
- 平時において連合会と共同店舗は災害に備えて協力方法や訓練、教育について取り決めを行う
- 災害発生時には被災した共同店舗に対する応急対応、復旧作業に従事する人員の派遣、応急支援物資の供給など、「災害時相互応援対応連携協定書」に基づき実施する
- 連合会、連携事業者の重要な情報はバックアップ体制を整える
想定されるリスク:積雪
リスク発生による影響
- 従業員の出社および帰宅が困難になり、営業が不能となる
- 駐車場が使用不能となり、お客さまの来店、従業員の出社が不可能となる
- 物流の停滞により仕入れ、配送ができなくなる
対応策と効果
※地震時の対応策と効果と同様
想定されるリスク:感染症
リスク発生による影響
- 感染症の発生に起因する移動制限で、従業員確保が難しくなり、営業不能が想定される
- 衛生用品が入手できなくなり、従業員の感染症防止対策を講じることができなくなる
対応策と効果
組合員の前向きな姿勢で計画策定はスムーズに
一方、策定にあたっては、「感染症対策」「地震対策」に加え、「大雪対策」も盛り込みました。
「このところのゲリラ豪雪で、福井県内でも道路での立ち往生など、交通の途絶が発生しています。また多すぎる積雪により施設の運営が困難になりましたので、そうした物流や店舗での対応も、計画に反映させました」(竹内氏)
事業継続力強化計画の策定で、組合員の連携力も強化
今回の策定にあたっては、各組合単位にも事業継続力強化計画の広がりが生まれ、地域と連携した災害対応の取り組みも進みました。
「連合会の前にLpa独自でも事業継続力強化計画を策定していたということを他の組合員が知り、それぞれが独自で事業継続力強化計画を策定する動きも出てきたのです。また『災害時等応援対応連携協定』の締結で、災害時に一時避難場所となるショッピングセンターなどの事業継続、早期復旧を目指し、地域の避難者を円滑に支援することを目指しています」(竹内氏)
また連合会は、この先の計画に向けても検討を進めています。
「事業継続力強化計画を策定できたことはもちろん大きな前進ですが、それに加え、各組合員が『災害時に地域を支える拠点』として同じ方向を目指すことができたのは、大きな効果だと思っています。また並行して福井市との防災協定なども進め、災害に強い街作りの一翼を担うこととなりました。今後は策定した計画をより具体化する作業、つまり『こうなったときはこうする』というマニュアルづくりを進めていきたいと思っています。また現在は盛り込まれていない大雨への対応も、早い段階で策定したいと思います。私たち連合会はこれまでもしっかりとした連携をとってきましたが、今回の事業継続力強化計画策定に向けての取り組みで、その連携がより強固になったと考えています。この連携を、全組合員の成長、さらには地域貢献に役立てていきたいですね」(竹内氏)
関連記事