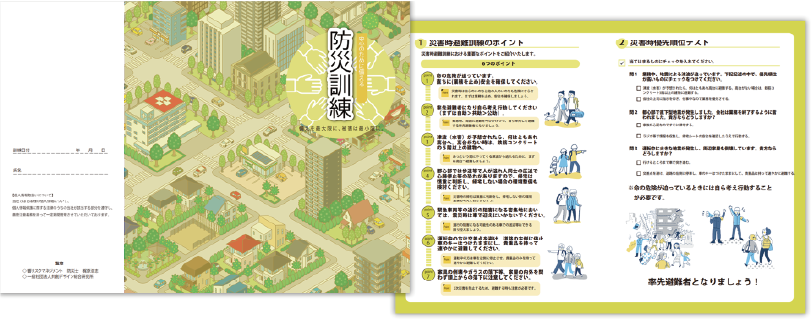サプライチェーンの事業継続力強化で地域貢献を

株式会社丸信
福岡県久留米市に本社を置く包装資材販売メーカー。「人びとが豊かに暮らす地域社会へ。」をビジョンに、包装資材、印刷物、ECサイト開発、HACCP認定のサポートなど多角的な事業を手がけ、お客さまの売上向上に貢献する。製品材料、生産資材を手がけるメーカーから食品メーカーなどに連なるサプライチェーンの中核をなす。
インタビュー(7分28秒)
卸売業から印刷事業に転換し急成長
筑後川がもたらす豊かな水と肥沃な筑後平野に恵まれた福岡県久留米市は、古くは農業で栄え、近代は絣や足袋の製造業からゴム産業へと大きく発展しました。さらに現代は、九州を南北軸、東西軸を結ぶ交通結節点としてその重要性を増しています。
株式会社丸信は、当地の特産品である干し椎茸の卸売会社の梱包資材を作る関連会社として、1968年に創業しました。
同社はこれまで、雇用、地域経済の活性化など、「地域貢献」への強い思いとともに歩んできました。そしてジギョケイの策定、申請も、その一環であると、平木氏は語ります。 「天災や感染症などを起因に事業継続が困難になると、その影響は業績だけでなく、弊社およびサプライチェーンの各社で働く従業員の雇用にもおよびますから」(平木氏)
事業継続を目的に損害保険でリスクをカバー
そうした課題への対応策のひとつとして同社が進めたのは、損害保険の見直しです。
「損害保険会社からリスクファイナンスの提案があり、当時加入している損保の契約内容について、《建物や設備・商品はどこまでが補償対象になっているか?》《保険金額はいくらか?》《補償対象となる災害や事故はどんな内容か?》といった内容をチェックする事からはじめました」(平木氏)
「保険料は決して安くはありませんが、やはり『地域貢献』を考える上で、事業継続はまず最優先すべきことです。そのためには保険料は“必要経費”だと考え、出しうる範囲での保険契約を結んでいます」(平木氏)
また、事業継続リスクの確認を進める中で、自然災害に限定せずに洗い出しを行ったところ、社有車での自動車事故が多発している事が明らかになりました。
「損保会社からの提案でドライブレコーダーを設置し、社員への注意を促しました。その結果、交通事故発生件数を大きく減らす事ができました。また、結果として自動車保険の保険料の削減にもつなげる事ができました。」(平木氏)
損害保険会社の後押しで連携型ジギョケイ策定へ
そして同社が連携型ジギョケイの策定、申請に踏み出したのも、この損害保険会社からの提案が直接のきっかけでした。
「もともと、過去にも事業継続の支障となった水害に重点を置き、単独型でのジギョケイ認定を取得していたのですが、より、強靭な体制を築くのにサプライチェーン全体で計画を作ってみてはどうかと提案をいただきました。」(平木氏)
提案を受け、機械や資材の仕入れ先である製造業者、また製品の出荷先である食品会社など、サプライチェーンを形成する事業者と連携してのジギョケイ策定にも乗り出しました。
「サプライチェーンを形成する事業者のいずれかが天災等で事業継続できなくなると、影響はサプライチェーン全体におよびます。そこで各事業者さまに、連携してのジギョケイへの取り組みを呼びかけたのです。ただ正直なところ、BCPへの意識は事業者によって温度差があります。そこで損害保険会社とともに、ジギョケイの認定はホームページでPRできること、また補助金申請において有利になることなどのメリットをお話しし、ご協力をお願いした次第です。理想とするサプライチェーンに連なる全事業者での連携は実現できませんでしたが、それは近い将来の目標として、今後も働きかけを続けることといたします」(平木氏)
想定されるリスク:水害
ハザードマップにより、サプライチェーン各社事業所で最大5mの浸水
リスク発生による影響
- 被災により従業員の多くが出勤できない可能性がある。
- 営業時間中の被災では設備の故障、不具合、避難中の転倒などにより負傷者や行方不明者が発生する。また帰宅困難者が発生する。
- 営業時間外の発生では、翌営業日の出社、参集が困難になる。
- 一部の連携事業者において浸水で建物や設備に被害が出るおそれがある。
- インフラや公共交通機関が機能不全となるおそれがある。
- 一部の連携事業者において、速やかな事業再開ができないため、売上が立たず、運転資金や復旧資金の確保が困難になる可能性がある。
- 一部の連携事業者で、通信途絶や浸水でサーバーの利用が困難になる、データが喪失する恐れがある。
対応策と効果
- 避難所までの経路確認等を「損害保険会社の災害時ナビ」等を活用し社内に徹底する。
- 顧客の避難場所の周知、誘導体制を確立する。
- 株式会社丸信では災害伝言ダイヤル、SNS、メールを活用し従業員の安否報告を行う。
- 連携事業者間で、平時の連絡会議を災害時対応会議に格上げし、発災後3時間以内に株式会社丸信代表取締役を本部長とした災害対策本部を立ち上げる。
- 各社の取り決めに従い被害情報を収集し、その有無にかかわらず、一定時間内に報告する。
- 被災事業者から要請等があった場合は復旧等に必要な人員を派遣する。
- 各事業者はグループ内に設置している保険代理店のアドバイスに従い、毎年保険手配について見直しを行う。
- 想定される損害に対する補償および資金調達手段の確保をするとともに、その情報を開示し、共有する。
- 重要情報をバックアップするためのサーバーを他の地域に設置する。
想定されるリスク:地震
警固断層を震源とする内陸型地震でサプライチェーンの一部に今後30年以内の地震発生確率は震度6弱67.9%、震度6強30.5%
リスク発生による影響
- 被災により従業員の多くが出勤できない可能性がある。
- 営業時間中の被災では設備の故障、不具合、避難中の転倒などにより負傷者や行方不明者が発生する。また帰宅困難者が発生する。
- 営業時間外の発生では、翌営業日の出社、参集が困難になる。
- 新耐震基準を満たしていない事業所の建物においては、建物や製造設備、商品が損傷する可能性がある。
- インフラや公共交通機関が機能不全となるおそれがある。
- 一部の連携事業者において、速やかな事業再開ができないため、売上が立たず、運転資金や復旧資金の確保が困難になる可能性がある。
- 一部の連携事業者で、通信途絶や地震による揺れでサーバーの利用が困難になる、データが喪失する恐れがある。
対応策と効果
※水害時の対応策と効果と同様
想定されるリスク:感染症
リスク発生による影響
- 国内で感染症が発生した場合、一部の連携事業者において移動制限、外出自粛要請などにより店舗等における必要な人員が確保できない可能性がある。
- 感染が拡大し従業員や家族が感染した場合は長期間出勤できなくなる従業員が複数発生し、担当顧客への業務引継ぎが滞る、営業停止を検討するなどして、顧客に迷惑をかけることになる。
- マスクや消毒液など衛生用品の入手が困難になることで、従業員の感染防止対策を講じることができなくなる。
- 従業員の出勤率を下げることによる生産ラインの稼働率の低下が想定される。
- 在宅勤務による情報漏洩が発生し、取引先への信用を失うなどの影響が想定される。
対応策と効果
- 国内で感染症の発生が確認された場合は、株式会社丸信で感染症対策の徹底を図る。
- 株式会社丸信では体調不良の従業員の出勤停止、交代勤務規定の整備、従業員やその家族の出勤前の検温を励行する。
- オンライン上の連絡会議の開催やメールを通じた情報共有を行う。
サプライチェーン一丸となって事業継続力を強化
今回のジギョケイでは、連携各事業者において、災害時に従業員を守るための対応のほか、被害状況の共有、さらには必要に応じての復旧等にあたる人員の相互派遣、施設の融通、代替生産の実施などが取り決められています。
「天災など事業継続にかかわる事態が発生したときは、弊社の駐車場や会議室を提供し、連携事業者が一丸となって復旧を目指す体制を構築します。弊社駐車場については周囲の土地よりも約2m高くする大規模なかさ上げ工事も完了しており、発生リスクが高い水害時でもその機能を十分に果たせるものと考えております」(平木氏)
こうして2022年11月にスタートした連携型のジギョケイは、その実効性を高めるため、日々の努力が続けられています。
「まだ弊社単独の取り組みですが、『命を大事に』を第一に、避難訓練を実施しています。私たちのノウハウが欠けている部分については、損害保険会社のサポートを仰ぎつつ、災害時に必要な防災、減災の備品関係のチェックを行う『寄り添いマップ』の提供、緊急時に従業員が適切に判断するためのチェックシートの開発などを進め、連携する事業者と共有するようにしています。また平時はとくに連絡会議などは設けていませんが、定期的なミーティングで交流を深め、いざというときの共助の意識の醸成に取り組んでいます」(平木氏)
さらに同社は、このジギョケイから一歩踏み出したBCP対策も進めています。
「たとえばふだんは外注している段ボール箱を作るときに使う抜き型については、ある程度は自社でも作れるものの、100%内製は不可能です。そのため、外注先で生産が困難になったとき、他地域の同種の事業者にデータを移管して生産を委託する手配は進めています。また弊社そのものが被災した場合には、ふだんは競合関係となっている同業他社に、一時的に生産を引き受けていただくような覚書も交わし、サプライチェーン全体が止まってしまうようなことがないよう対策しています」(平木氏)
生産拠点の多重化などさらなるリスク対応力を
また同社そのものの“災害対応力”についても、一段上を目指す努力が続けられています。
「現在、建設を進めている新工場は、駐車場と同様に約2m土地をかさ上げし、その上にプラットフォームを設置して設備を配置する設計となっています。これにより現状よりも格段に水害への対応力が上がることになります。また過去にはこの地域に直接的な影響のない水害でも、道路網の寸断により運送会社の集荷ネットワークが機能しなくなり、製造には問題がないのに製品の出荷ができないということもありました。そこで近畿地方で下請け生産を主力としている事業者の工場に弊社が設備を提供して生産の一部を移管し、緊急時にはそちらでの生産を拡大するような取り組みも現在進行中です」(平木氏)
関連記事